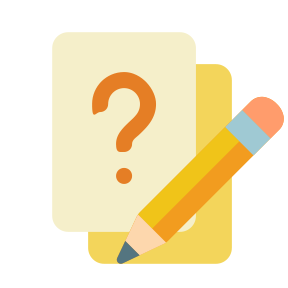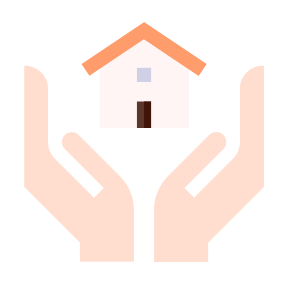亡くなった親の隠れた財産・借金が心配な方へ

親の相続財産を正確に
把握したい方へ
親の財産や借金の全容がわからず、相続手続きに不安を感じていませんか?隠れた借金が後から発覚して返済義務を負うことになるのではと心配していませんか?見落としている財産があるかもしれないと気になっていませんか?
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
親の財産・借金を
調査する方法
親が亡くなった後の財産や借金の調査は、相続手続きを安全に進めるために極めて重要です。弁護士は相続財産の調査に関する専門知識を持ち、見落としがちな財産や隠れた借金を発見するための適切な方法をアドバイスできます。また、調査結果に基づいて、単純承認・限定承認・相続放棄のどの選択肢が最適かについても助言可能です。専門家のサポートを受けることで、将来の思わぬトラブルを防ぎ、安心して相続手続きを進めることができます。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
相続財産調査とは
相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や借金の全容を把握するための手続きです。日本の相続法では、被相続人の財産と債務はセットで相続されるため、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も正確に把握する必要があります。相続開始後の熟慮期間(3ヶ月)内に調査を行い、相続を受け入れるか放棄するかの判断材料とします。適切な調査は、将来の相続人間トラブルや予期せぬ債務負担を防ぐための重要なステップです。
相続財産調査の特徴

預貯金・不動産・有価証券などのプラス財産の調査
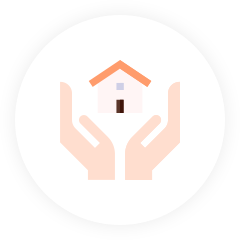
借金・ローン・保証債務などのマイナス財産の調査

生命保険や退職金など見落としやすい財産の確認

デジタル資産(暗号資産・オンライン口座)の調査

貸付金や知的財産権など特殊な財産の調査
To Do
相続財産を調査するための5つの方法

自宅に残された書類
や通帳を確認する
まずは親の自宅に残された書類や通帳を確認しましょう。預金通帳・証書、保険証券、不動産の権利書、固定資産税の納税通知書、株券・投資信託の取引報告書、クレジットカードの明細、年金手帳、確定申告書の控え、借用書・契約書などがないか探します。
Point
書類を探す際は、親が使っていた書斎や机の引き出しだけでなく、本棚の間、タンスの奥など、普段目にしない場所も丁寧に確認することが重要です。また、貸金庫を利用していた可能性も考慮し、銀行の通帳や明細書に貸金庫の利用料金が引き落とされていないかチェックしましょう。調査の初期段階で見つかった書類から、さらに調査すべき財産や取引先の手がかりが得られます。

金融機関で預貯金
や借入金を調査する
親が利用していた金融機関を訪問し、預貯金や借入金の有無を確認します。相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)と親の死亡を証明する書類(死亡診断書など)、本人確認書類を持参して照会しましょう。

不動産の所有状況
を確認する
親が所有していた不動産は、市区町村役場で固定資産課税台帳を取得したり、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して確認できます。親の本籍地や最後の住所地を管轄する法務局で調査を行いましょう。また、固定資産税の納税通知書からも、所有不動産の情報を把握できます。不動産の評価額は、相続税申告の際に重要になります。

生命保険や退職金など
見落としやすい財産を調べる
現金や不動産以外にも、見落としがちな財産があります。生命保険は保険証券を探すか、生命保険協会の「契約照会制度」を利用して調査しましょう。退職金・企業年金は親の勤務先に確認します。株式・投資信託は証券会社の取引報告書を探すか、取引のあった証券会社に照会します。これらの財産は相続財産として重要です。

借金や保証債務の
有無を確認する
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も正確に把握することが重要です。住宅ローンやその他の借入金は、契約書や返済明細書を確認するか、金融機関に照会します。クレジットカード債務は、カード会社に連絡して未払い残高を確認しましょう。特に注意が必要なのは連帯保証債務で、契約書を探すか、親が取引していた金融機関に保証債務の有無を照会することが大切です。
Point
Point
相続財産調査における2つのポイント

徹底的な調査で隠れた財産・借金を見つける
相続財産の調査では、表面的な確認だけでなく、徹底的な調査が重要です。最初に見つかった手がかりをもとに調査範囲を広げていくことで、隠れた財産や借金を発見できる可能性が高まります。例えば、確定申告書の利子所得から把握していなかった預金口座の存在がわかったり、クレジットカードの明細から知らなかった取引先が判明したりすることもあります。デジタル資産(暗号資産・オンライン口座)やパソコン・スマートフォン内の情報も重要な手がかりとなります。調査にはある程度の時間と労力がかかりますが、将来のトラブルを防ぐために必要な投資と考えましょう。

3ヶ月の期限を意識した計画的な調査
相続の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)には、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内という期限があります。この期限を過ぎると、原則として単純承認(全ての財産と借金を引き継ぐ)となってしまうため、計画的な調査が不可欠です。特に借金が見つかり始めた場合は、相続放棄の可能性も考慮して、早めに調査を進めることが重要です。調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることも選択肢の一つです。また、専門家(弁護士・司法書士など)に相談することで、効率的な調査と適切な判断が可能になります。
相続財産調査を適切に行うために
相続財産調査では、被相続人の全ての財産と債務を漏れなく把握することが重要です。不動産・預貯金・有価証券・借金などを系統的に調査し、財産目録を作成して相続人全員で共有しましょう。
金融機関への残高証明書請求、法務局での登記簿謄本取得、信用情報機関での借入状況確認など、適切な手続きを行うことで見落としを防げます。必要に応じて司法書士や弁護士に依頼し、透明性の高い調査を実施することで公平な遺産分割の基盤を築きましょう。
Victim
相続財産調査で悩む相続人の心理

不安と責任に
向き合う方法
親の死後、相続財産の調査を担当する相続人は大きな不安と責任を感じるものです。「隠れた借金があるのではないか」「財産を見落として他の相続人に迷惑をかけるのではないか」といった心配が生じることは自然なことです。こうした不安を一人で抱え込まず、他の相続人と協力して調査を進めたり、専門家に相談したりすることで、精神的な負担を軽減できます。また、調査は完璧を目指すよりも、できる限りの努力をしたうえで、必要に応じて専門家の力を借りる姿勢が大切です。

安心できる相続
への第一歩
財産調査は面倒で時間のかかる作業ですが、この調査が安心できる相続への第一歩となります。正確な調査を行うことで、将来の予期せぬトラブルを防ぎ、親の遺志を尊重した相続を実現することができます。また、調査の過程で親の生前の努力や慎重な資産管理の跡を発見することもあり、それが親への感謝や尊敬の気持ちにつながることもあります。弁護士のサポートを受けながら、法的に適切な対応をとることで、相続人全員が納得できる形で相続を進めることができます。
Sample
Price
相続財産調査に関わる費用の相場

相続財産調査の一般的な費用
相続財産調査にかかる費用は、調査の範囲や専門家への依頼内容によって大きく異なります。自分で調査する場合は、戸籍謄本等の取得費用(1通300〜450円程度)、登記簿謄本の取得費用(1通500〜600円程度)などの実費が主な費用となります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、基本報酬として10〜30万円程度、財産額に応じた報酬として相続財産の0.5〜2%程度が一般的な相場です。調査の複雑さや財産の種類・規模によって費用は変動します。特に不動産が多い場合や事業用資産がある場合、海外財産がある場合などは、調査費用が高くなる傾向があります。


信頼できる専門家の選び方
相続財産調査のサポートを依頼する専門家選びでは、まず相続分野の実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
相続財産調査に関するよくあるご質問
Q
相続財産の調査は全ての相続人が行う必要がありますか?
相続財産の調査は、必ずしも全ての相続人が行う必要はありません。
通常は、被相続人と同居していた相続人や、相続手続きを中心的に担当する相続人が調査を行うことが多いです。ただし、調査結果は全ての相続人で共有し、重要な判断(相続放棄するかどうかなど)は全員で行うことが望ましいです。また、相続人の一人が独自に調査を進めると、他の相続人から不信感を持たれる可能性もあるため、事前に調査の進め方について話し合っておくことが重要です。
Q
相続財産の調査は時間がかかりそうですが、3ヶ月の期限までに間に合わない場合はどうすればよいですか?
相続の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)の期限である3ヶ月以内に調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。
この申立てが認められれば、期限を延長できます。申立ては相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、調査に時間がかかる合理的な理由(財産が多い、海外にも財産がある、書類が見つからないなど)が必要です。申立ての際は、これまでの調査状況や今後の調査計画を具体的に説明できるよう準備しておくことが大切です。
Q
なぜ弁護士に相談すべきでしょうか?
弁護士は相続財産調査に関する専門知識と経験を持っています。
特特に財産状況が複雑な場合や、借金が見つかり始めた場合、他の相続人との関係が難しい場合などは、専門家のサポートが大きな助けとなります。弁護士に相談することで、調査すべき財産の種類や調査方法について具体的なアドバイスを受けられるだけでなく、調査結果に基づいて相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)についての適切な助言も得られます。また、期限内に調査を完了するための効率的な進め方や、必要に応じて熟慮期間の延長申立てのサポートも受けられます。相続は一生に何度も経験するものではないため、専門家の力を借りることで安心して手続きを進めることができます。