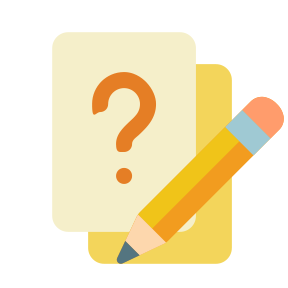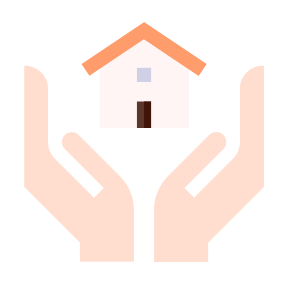後悔しない遺言書の残し方

効力を確実に発揮する書き方
大切な家族や愛する人々へのメッセージと財産を遺すための「遺言書」作成を検討しませんか?「どのように書けばよいのか」「法的に有効な遺言書とは何か」と悩まれる方に向けて、後悔しない遺言書の残し方から、効力を確実に発揮する書き方、そして相続開始後の手続きを理解して行動を起こしましょう。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
後悔しない
遺言書作成の方法
遺言書は、あなたの意思を伝える重要な法的文書です。弁護士は遺言書作成に関する専門知識を持ち、法的に有効な遺言書の作成をサポートできます。特に相続関係が複雑なケースや、特定の財産を特定の相続人に確実に引き継がせたい場合には、専門家のアドバイスが解決の糸口になります。専門家のサポートを受けることで、遺言書の形式不備等により無効になってしまうことを防ぎ、あなたの意思を正確に反映した遺言書を作成することができます。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
遺言書とは
遺言書とは、被相続人(遺言を遺す人)の死後に財産をどのように分配するかなどの意思を記した法的文書です。民法で定められた方式に従って作成する必要があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は相続に関する様々な内容を指定できる強力な文書です。遺言書がない場合は民法で定められた法定相続分に基づいて遺産分割が行われます。しかし、それでは必ずしも被相続人の意思が反映されず、相続人間での争いや、不動産の共有状態による管理の難航、事業承継の問題などのトラブルが発生する可能性があります。遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝え、相続トラブルを予防し、財産の分配を自由に決められるというメリットがあります。
遺言書作成のポイント

15歳以上であれば誰でも作成できる
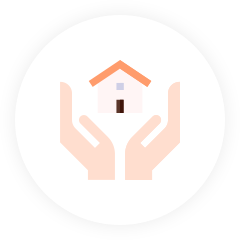
作成方法によって3種類ある

法律で定められた形式に従わないと無効になる

相続人以外の人にも財産を遺せる(遺贈)

法定相続分とは異なる分配も可能
To Do
すぐに始める遺言書作成の5つの方法

遺言書の種類
を選択しよう
まずは自分に合った遺言書の種類を選びましょう。自筆証書遺言は費用がかからず簡単に作成できますが、形式不備のリスクがあります。公正証書遺言は専門家が関与するため法的安全性が高く、原本が公証役場で保管されます。秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま公証人に証明してもらう方法です。あなたの状況、希望、予算などを考慮して最適な種類を選びましょう。
Point
遺言書の種類選びは、作成の手軽さと法的安全性のバランスを考慮することが重要です。自筆証書遺言は、費用をかけずに自分のペースで作成できる反面、形式不備による無効のリスクがあります。しかし、2020年7月からは「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まり、自筆証書遺言について、形式面のチェックを受けた上で法務局で保管してもらえるようになりましたので、この点も考慮して検討する必要があります。一方、公正証書遺言は費用がかかるものの、公証人の専門的知識により方式不備のリスクが低く、原本が公証役場で保管されるため紛失や偽造のリスクもありません。

記載内容を
具体的に検討しよう
遺言書に記載する内容を具体的に検討しましょう。主な記載事項としては、財産の分配方法(誰にどの財産を相続させるか)、相続分の指定(法定相続分と異なる割合での指定)、遺贈(相続人以外への財産の贈与)、遺言執行者の指定などがあります。財産は特定できるよう具体的に記述することが重要です。不動産であれば所在地と地番、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号などを明記しましょう。

形式要件を確認しよう
選んだ遺言書の種類に応じた形式要件を確認しましょう。自筆証書遺言の場合は、全文を自筆で記載し、日付と氏名を記載して押印する必要があります。公正証書遺言の場合は、公証人への依頼、証人2名の手配、必要書類の準備などが必要です。秘密証書遺言の場合は、遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2名の前で所定の手続きを行う必要があります。法的に有効な遺言書にするためには、これらの形式要件を厳格に守ることが重要です。

保管方法
を決めよう
作成した遺言書の保管方法を決めましょう。自筆証書遺言の場合は、2020年7月から始まった「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討するとよいでしょう。この制度を利用すると、遺言書の紛失・偽造・変造のリスクが減少し、家庭裁判所の検認手続きも不要になります。公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されますが、謄本を自分でも保管しておくとよいでしょう。保管場所は信頼できる人に伝えておくことも重要です。

速やかに専門家
に相談しよう
遺言書作成に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。特に相続関係が複雑な場合(再婚している、海外に住む相続人がいるなど)、事業承継を含む相続を考える場合、相続税対策と連動させたい場合などは、専門家のアドバイスが重要です。弁護士に相談することで、法的に有効な遺言書の作成だけでなく、相続全体のプランニングについてアドバイスを受けることができます。早めの相談が後々のトラブル防止につながります。
Point
Point
遺言書作成における2つのポイント

曖昧な表現を避け明確に意思を伝える
遺言書では、曖昧な表現を避け、明確に意思を伝えることが非常に重要です。例えば「財産を長男と次男に平等に分ける」という表現は、具体的にどの財産をどのように分けるかが不明確で、解釈に争いが生じる可能性があります。代わりに「Aという不動産は長男に、B銀行の預金は次男に相続させる」というように具体的に記載しましょう。
また、「形見の品々を子どもたちに与える」という表現も曖昧です。「金の指輪は長女に、腕時計は長男に、ピアノは次女に与える」というように、具体的な品物と相続人・受遺者を明確に指定することが重要です。

遺留分を考慮した内容にしよう
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母)には法定相続分の1/2又は1/3の遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する内容の遺言も法的には有効ですが、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」をすることができます。例えば、配偶者と2人の子がいる場合に、全財産を長男に相続させる遺言を書いたとしても、配偶者と次男は遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺言書作成の具体的な手続き
遺言書作成のプロセスは、情報収集と検討(1〜2週間)、内容の決定と形式選択(1〜2週間)、遺言書の作成(自筆証書遺言は数時間、公正証書遺言は1〜2週間)という流れで進行します。
自筆証書遺言の場合は、全文を自筆で書き、日付と氏名を記載し押印します。公正証書遺言の場合は、公証役場に予約を入れ、必要書類を準備し、証人2名と共に公証役場で手続きを行います。法務局での保管を希望する場合は、最寄りの法務局に予約し、遺言書と本人確認書類を持参して手続きを行います。
Victim
遺言書作成に関する不安

遺言書作成の先送り
による後悔
遺言書の作成は「まだ早い」「まだ先のこと」と先送りにしがちな問題です。しかし、突然の事故や病気で判断能力が低下してしまうと、有効な遺言書を作成できなくなる可能性があります。また、遺言書を残さないまま亡くなると、相続人間の争いが生じたり、想定外の財産分配になったりするリスクがあります。
こうした不安を軽減するために、早めに遺言書の作成に着手することが大切です。健康なうちに、冷静な判断で遺言書を作成しておくことで、将来の不安を取り除き、大切な人たちに余計な負担をかけないようにすることができます。

遺言書による
安心感の獲得
有効な遺言書を作成することで、自分の死後に関する不安を軽減し、精神的な安心感を得ることができます。特に、自分の希望通りに財産が引き継がれるか、大切な人たちの間で争いが生じないか、といった心配は大きなストレスになります。
弁護士のサポートを受けながら法的に有効な遺言書を作成することで、これらの不安を解消し、自分の意思が確実に実現されるという安心感を得られます。また、遺言書作成のプロセスを通じて、自分の財産の全体像を把握したり、家族との関係を見つめ直したりする機会にもなります。
Sample
Price
遺言書作成にかかる費用の相場

遺言書作成の一般的な費用
遺言書作成にかかる費用は、選択する遺言書の種類によって大きく異なります。
自筆証書遺言は基本的に費用がかかりませんが、法務局で保管する場合は1通につき3,900円の手数料がかかります。また、相続開始後に検認が必要な場合は、家庭裁判所への手数料(800円程度)が発生します。
公正証書遺言の場合は、公証人手数料が発生します。手数料は遺言書に記載される財産の価額によって変動し、一般的には5〜15万円程度です。これに加えて証人も公証役場で準備してもらう場合には、謝礼(1人あたり5,000〜10,000円程度)も必要になります。


信頼できる専門家の選び方
遺言書作成のサポートを依頼する専門家選びでは、まず遺言・相続に関する実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。追加料金の発生条件や最終的な総額が明確に提示されるべきです。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
遺言書作成に関するよくあるご質問
Q
遺言書を何度も書き直したい場合、どうすればよいですか?
遺言者は判断能力がある限り、いつでも遺言を変更できます。
新しい遺言書を作成し「前の遺言を撤回する」と明記するか、自筆証書遺言なら破棄することで撤回できます。複数の遺言書が見つかった場合は、原則として日付が新しいものが優先されます。状況の変化に応じて定期的に見直しましょう。
Q
遺言執行者は誰に指定すればよいですか?
遺言執行者は信頼できる人物を選びましょう。
適任者の条件は、公平な立場で遺言を執行できること、基本的な財産管理の知識があること、遺言者の死後も任務を遂行できる可能性が高いことです。親族、弁護士・司法書士、信託銀行などが候補となります。特に相続人間で対立が予想される場合は、中立的な専門家を指定することをお勧めします。
Q
遺言書で財産をすべて一人に相続させることはできますか?
法律上は可能ですが、遺留分の問題があります。
配偶者、子、直系尊属には法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)の遺留分が保障されています。全財産を一人に相続させる遺言も有効ですが、他の遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすると、金銭での支払いが必要になります。遺留分の問題を回避するために、専門家に相談して最適な方法を検討しましょう。