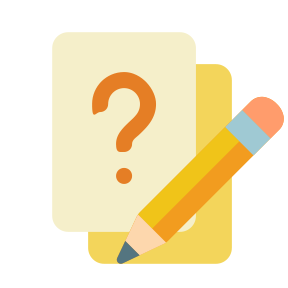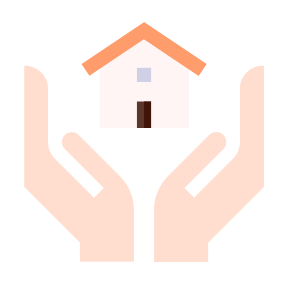生前贈与で減った遺産と相続権を守る

生前贈与で減った遺産と相続権を守る
相続においてしばしば問題となるのが、被相続人(亡くなった方)が生前に特定の相続人に多額の財産を贈与していた場合です。このような生前贈与によって遺産が減少していると、他の相続人は期待していた相続財産を受け取れないこともあります。生前贈与により減少した遺産に対する法的な保護制度である「遺留分」と「特別受益」について理解して行動を起こしましょう。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
生前贈与で減った遺産に関する問題を解決する方法
生前贈与により遺産が減少した場合でも、法律は「遺留分」という制度を通じて相続人の権利を保護しています。遺留分とは、相続人に法律上保障された最低限の取り分であり、生前贈与や遺言によってもこの権利を奪うことはできません。弁護士は遺留分に関する専門知識を持ち、あなたの正当な権利を守るためのサポートができます。また、「特別受益」の考え方を活用することで、より公平な遺産分割を実現することも可能です。専門家のサポートを受けることで、複雑な計算や請求手続きの負担を軽減し、あなたの相続権を適切に守ることができます。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を無償で他者(多くの場合は家族)に譲り渡すことです。民法上は「贈与契約」として位置づけられており、財産権を無償で相手に移転する約束をすることで成立します。相続税対策として広く活用され、現行制度では年間110万円までの贈与であれば贈与税が非課税となる「暦年贈与」や、60歳以上の親から18歳以上の子や孫に対して2,500万円までの特別控除がある「相続時精算課税制度」などがあります。生前贈与は一度成立すると原則として贈与者の一方的な意思で取り消すことができないため、遺言とは異なり法的拘束力が強いという特徴があります。しかし、このような生前贈与が特定の相続人に偏っていると、他の相続人の取り分が減少し、相続トラブルの原因となることがあります。
生前贈与による相続問題の特徴

特定の相続人だけが多額の贈与を受け、不公平が生じる
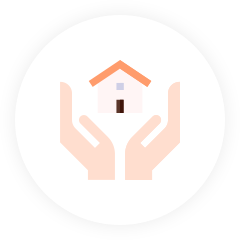
贈与により相続財産自体が大幅に減少している

相続開始前に贈与されているため取り戻しが難しい

贈与の事実や金額の立証が困難なケースがある

贈与税の観点と相続法の観点で扱いが異なる
To Do
生前贈与により減った遺産に対応するための5つの方法

遺留分の有無と金額
を確認しよう
まずは自分の遺留分の有無と金額を確認しましょう。遺留分があるのは配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(親・祖父母)のみで、兄弟姉妹には認められていません。遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。具体的な金額は、相続財産に生前贈与などの特別受益を加算し、債務を控除した金額に遺留分割合をかけて算出します。
Point
遺留分の計算は専門的で複雑ですが、その基本を理解しておくことは重要です。計算の基礎となる財産には、実際に相続される財産だけでなく、被相続人が亡くなる前の一定期間内(原則1年以内(他の相続人への贈与の場合には10年以内)、ただし当事者が遺留分侵害を知っていた場合は期間制限なし)に行われた贈与も含まれます。また、2019年7月の民法改正により、遺留分制度は「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと変わり、不動産などの現物返還ではなく、金銭による請求という形に変更されました。この改正により、生前贈与を受けた相続人は財産を手放す必要はなくなりましたが、代わりに金銭で支払う義務が生じる可能性があります。遺留分の計算に不安がある場合は、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。

特別受益に該当する
贈与かどうかを判断しよう
生前贈与が「特別受益」に該当するかどうかを判断しましょう。特別受益とは、被相続人から相続人が受けた生前贈与や、結婚・養子縁組のための出費(婚姻費用等)のことです。不動産や高額な動産の贈与、住宅取得資金の援助、事業資金の援助、多額の結婚資金などが典型例ですが、通常の教育費や生活費の援助、一般的な冠婚葬祭費用などは特別受益には含まれません。贈与の時期や金額、当時の社会通念なども判断材料になります。

遺留分侵害額
を計算しよう
特別受益を含めた相続財産全体に対する自分の遺留分と、実際に受け取れる遺産額を比較して、遺留分侵害額を計算しましょう。例えば、遺産が3,000万円、特別受益が1,000万円、債務が500万円の場合、計算の基礎となる財産額は3,500万円(3,000万円+1,000万円-500万円)です。子が2人いる場合、各子の遺留分は875万円(3,500万円×1/2×1/2)となります。もし実際に受け取れる遺産が875万円より少なければ、その差額が遺留分侵害額となります。

遺留分侵害額請求
の手続きを始めよう
遺留分侵害額があることが確認できたら、具体的な請求手続きを進めましょう。まずは受遺者や受贈者に対して、内容証明郵便などで遺留分侵害額の請求を行いましょう。当事者間で協議を行い、支払い金額や支払い方法について合意を目指しましょう。協議が整わない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。請求権の行使は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」または「相続開始の時から10年間」のいずれか早い方が経過すると時効となるため、早めの対応が重要です。

専門家に相談し
法的アドバイスを受けよう
遺留分や特別受益の問題は法律的に複雑なため、弁護士などの専門家に相談しましょう。弁護士は遺留分侵害額の計算方法や請求手続き、交渉方法などについて専門的なアドバイスを提供してくれます。また、家族間のトラブルに発展しないよう、円満な解決に向けたサポートも期待できます。早い段階での相談が問題解決の鍵となります。
Point
Point
遺留分と特別受益に関する2つのポイント

特別受益の「持ち戻し」計算をマスターしよう
特別受益の「持ち戻し」とは、公平な相続を実現するための計算方法です。相続財産に特別受益の価額を加えた上で各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた相続人の相続分からその特別受益の価額を控除します。これにより、生前贈与などで先に財産を受け取った相続人と、そうでない相続人との間の不公平を是正できます。
例えば、父親の遺産が2,000万円で、長男が生前に1,000万円の贈与を受けていた場合、特別受益の持ち戻し計算では、まず相続財産を3,000万円(遺産2,000万円+特別受益1,000万円)として考えます。長男と次男の法定相続分が各1/2とすると、本来各人の取り分は1,500万円ずつとなります。長男は既に1,000万円を受け取っているので、残りの遺産2,000万円からは500万円を受け取ることになり、次男は1,500万円を受け取ることになります。
この計算は遺産分割協議においても重要な指針となります。ただし、特別受益の持ち戻しは遺言で免除することもできます。また、相続人全員の合意があれば、特別受益を考慮しない分割方法を選択することも可能です。しかし、合意が得られない場合には、この持ち戻し計算が基準となることを理解しておきましょう。

遺留分侵害額請求の時効管理と証拠収集を始めよう
遺留分侵害額請求権には時効があります。「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」または「相続開始の時から10年間」のいずれか早い方が経過すると消滅するため、時効管理が重要です。特に隠れた生前贈与が後から発覚した場合でも、それを知った時点から1年以内に請求する必要があります。
また、生前贈与の事実や金額を証明するための証拠収集も重要です。被相続人の銀行取引明細、贈与契約書、不動産登記簿、贈与税の申告書など、贈与の事実を裏付ける資料を可能な限り収集しましょう。親族間の贈与は口頭で行われることも多く、証拠が乏しいケースもありますが、間接的な証拠や状況証拠も含めて収集することが大切です。
必要に応じて、内容証明郵便で生前贈与の事実確認を求めたり、弁護士を通じて調査を行ったりすることも検討しましょう。証拠が不十分な状態で遺留分侵害額請求を行うと、請求額の算定が難しくなったり、請求自体が認められない可能性もあります。早い段階で専門家に相談し、適切な証拠収集と時効管理を行うことが成功の鍵となります。
生前贈与と遺留分で困らないために
生前贈与による遺留分侵害への対応プロセスは、事実確認と証拠収集(1〜2ヶ月)、遺留分侵害額の計算(2〜4週間)、請求と交渉(1〜3ヶ月)、必要に応じた訴訟(6ヶ月〜1年半)という流れで進行します。シンプルなケースで3〜6ヶ月、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。
遺留分侵害額請求に必要な書類は、被相続人と相続人の戸籍謄本、遺産の評価資料(不動産登記簿、固定資産評価証明書など)、生前贈与の証拠(契約書、振込記録など)、債務に関する資料などです。請求は内容証明郵便で行うことが一般的で、協議が整わない場合は訴状や証拠書類を準備して裁判所に提出します。
Victim
生前贈与と遺留分に関する心理

家族関係の悪化
への不安
遺留分侵害額請求を行うことで、家族関係が悪化するのではないかという不安を感じる方は少なくありません。「お金のことで家族と争いたくない」「兄弟との関係が壊れるのではないか」といった心配は自然なことです。特に、生前贈与を受けた相続人が「親の意思だった」と主張するケースでは、感情的な対立に発展しやすくなります。

遺留分制度による
公平な相続の実現
遺留分制度は、被相続人の意思だけでなく、一定の相続人に最低限の財産を保障するという法の理念を実現するためのものです。この制度を適切に活用することで、生前贈与によって生じた不公平を是正し、相続人間の公平性を確保することができます。弁護士のサポートを受けながら法的に適切な対応をとることで、感情的な対立を最小限に抑えつつ、あなたの正当な権利を守ることができます。遺留分侵害額請求の手続きは複雑ですが、専門家の助けを借りることで負担を軽減できます。
Sample
Price
生前贈与と遺留分の相場

遺留分侵害額請求の一般的な費用
遺留分侵害額請求にかかる費用は、自分で行う場合と弁護士に依頼する場合で大きく異なります。自分で手続きを行う場合の主な費用は、内容証明郵便の送付費用(1,000円程度)、戸籍謄本等の取得費用(1通300〜450円)、訴訟を提起する場合の印紙代(請求額に応じて変動)などです。
弁護士に依頼する場合は、着手金として20〜50万円程度、成功報酬として回収額の10〜20%程度が一般的です。ただし、案件の複雑さや財産の金額によって変動します。また、訴訟になった場合は別途費用が発生することがあります。


信頼できる専門家の選び方
相続問題のサポートを依頼する専門家選びでは、まず遺留分や特別受益に関する実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
生前贈与と遺留分に関するよくあるご質問
Q
遺留分は誰にでも認められる権利ですか?
いいえ、遺留分は全ての相続人に認められているわけではありません。
遺留分が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(親・祖父母)のみです。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合は相続人の種類によって異なります。直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子が相続人の場合)は法定相続分の2分の1です。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子はそれぞれ4分の1ですので、配偶者の遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)、子はそれぞれ8分の1(4分の1×2分の1)となります。
また、遺留分は放棄することも可能です。ただし、放棄は相続開始前に家庭裁判所の許可を得て行う必要があり、一度放棄すると原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。相続開始後に遺留分を放棄することは、実質的には遺留分侵害額請求権を行使しないという選択になります。
遺留分が認められているかどうかは、相続における重要な権利の違いになりますので、自分の立場を正確に理解しておくことが大切です。
Q
小規模宅地等の特例とはどのような制度で、どのような要件がありますか?
生前贈与のうち、どのようなものが特別受益に該当しますか?
生前贈与のうち特別受益に該当するかどうかは、贈与の内容や金額、社会通念などを総合的に判断します。一般的に以下のようなものが特別受益に該当します。
特別受益に該当する典型例:
- 不動産(土地・建物)の贈与
- 高額な動産(自動車、貴金属、美術品など)の贈与
- まとまった住宅取得資金や事業資金の援助
- 多額の結婚資金の援助(社会通念を超える金額)
- 債務の肩代わり
特別受益に該当しない典型例:
- 通常の範囲内の教育費(学費、塾や習い事の費用など)
- 日常生活費の援助
- 一般的な範囲内の冠婚葬祭費用
- 社会通念上相当と認められる程度の結婚祝い金
- 誕生日や記念日のプレゼント
判断が難しいケースもあります。例えば、医学部など特に高額な学費がかかる教育を受けさせた場合、通常の教育費を超える部分については特別受益と認められる可能性があります。また、同居して介護などをしていた相続人に対する生活費の援助は、その実質が報酬的な性格を持つ場合は特別受益に該当しないこともあります。
特別受益の判断は個別のケースによって異なりますので、明確な基準がないケースでは専門家に相談することをお勧めします。
Q
遺留分侵害額請求をしたら、不動産の贈与を取り消せますか?
2019年7月の民法改正以前は、「遺留分減殺請求」として、不動産などの贈与された財産そのものの返還を求めることが可能でした。
しかし、改正後は「遺留分侵害額請求」となり、基本的には金銭での支払いを請求する権利に変わりました。つまり、現行制度では、生前贈与で譲渡された不動産そのものを取り戻すことはできません。
例えば、父親が長男に2,000万円相当の不動産を生前贈与し、その他の遺産が1,000万円あるケースを考えましょう。長男と次男の2人が相続人の場合、次男の遺留分は750万円(遺産1,000万円+生前贈与2,000万円=3,000万円、その1/2×1/2)となります。実際に次男が相続できる財産は1,000万円×1/2=500万円なので、遺留分侵害額は750万円-500万円=250万円となります。次男は長男に対して、この250万円の支払いを請求できますが、不動産そのものの返還を求めることはできません。
ただし、例外的なケースとして、受贈者(不動産を贈与された人)が金銭による支払いが難しい場合、裁判所の許可を得て不動産の一部や全部を返還することで、遺留分侵害額の支払いに代えることができる制度(代物弁済)があります。また、当事者間の合意があれば、不動産の返還という形で解決することも可能です。
いずれにしても、現行制度の原則は金銭による清算であり、不動産の返還を第一の選択肢として考えることはできなくなっていることを理解しておきましょう。