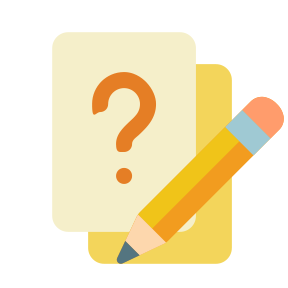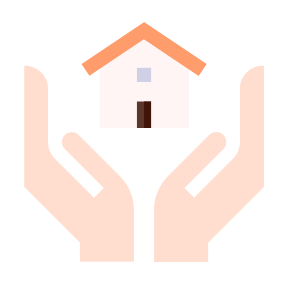認知症になった親の財産を守る成年後見制度

認知症になった親の財産を守る成年後見制度
親の認知症が進行すると、財産管理や契約行為など日常生活の法律行為が困難になります。成年後見制度は認知症などにより判断能力が不十分な方を法律面で支援する重要な制度です。成年後見制度の基礎知識から申立て手続きを理解していきましょう。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
認知症の
親の財産を守る方法
認知症の親の財産を守るためには、成年後見制度の活用が効果的です。弁護士は成年後見制度に関する専門知識を持ち、申立て手続きから後見人の職務まで包括的にサポートできます。特に複雑な財産管理や親族間に意見の相違がある場合は、法律の専門家である弁護士のサポートが解決の鍵となります。成年後見制度により、親の財産を不正な契約や詐欺から守り、適切な管理と本人の意思を尊重した生活を実現できます。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
Case
成年後見制度とはとは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方(本人)を法律的に支援・保護するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の代わりに財産管理や契約などの法律行為を行い、本人の権利と財産を守ります。この制度には、判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、また、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度は本人の判断能力が低下した後に申し立てるもので、任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちに将来に備えて契約を結ぶものです。
成年後見制度の特徴

家庭裁判所が成年後見人を選任・監督
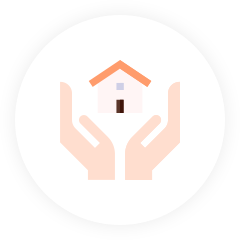
本人の判断能力に応じて3つの類型

成年後見人は本人の財産管理と身上保護を行う

後見人には親族や弁護士など専門職が選ばれる

成年後見登記され第三者への対抗力を持つ
To Do
成年後見制度を利用するための5つのステップ

親の判断能力
の程度を見極める
成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。親の認知症の進行状況や判断能力の程度を見極め、適切な類型を選びましょう。「後見」は判断能力が欠けている場合、「保佐」は著しく不十分な場合、「補助」は不十分な場合に適用されます。医師の診断書や日常生活での様子が判断材料になります。
Point
判断能力の程度を客観的に把握するためには、専門医への受診が重要です。物忘れ外来や認知症外来がある医療機関を受診し、認知機能検査を受けることで、認知症の程度や判断能力の状態を医学的に評価してもらえます。医師の診断書は後見申立ての際の重要な資料となります。

申立てに
必要な書類を準備する
家庭裁判所への申立てには多くの書類が必要です。申立書、医師の診断書、本人と申立人の戸籍謄本、住民票、親族関係図、財産目録、収支予定表などを準備します。特に診断書は指定の書式があるため、事前に家庭裁判所から取り寄せておきましょう。

家庭裁判所
に申立てを行う
準備した書類を本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。収入印紙3400円と連絡用の郵便切手が必要です(申立て後、鑑定費用もかかる可能性があります。)。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。申立て後、裁判所から本人と申立人に面談の案内が来ます。

後見人候補者
を検討する
成年後見人には、親族や弁護士・司法書士などの専門職がなることができます。候補者を検討する際は、財産管理能力、本人との関係性、利益相反の有無などを考慮しましょう。複雑な財産管理が必要な場合や親族間に争いがある場合は、中立的な立場の専門職後見人が選ばれることが多いです。

審判後の
後見事務を理解する
家庭裁判所の審判により成年後見人が選任されると、後見業務が始まります。財産の調査・目録作成、定期的な収支管理、必要な契約手続き、年1回の家庭裁判所への報告などが主な業務です。後見人は本人の意思を尊重し、本人の財産を適切に管理・活用することが求められます。
Point
Point
成年後見制度における2つのポイント

法定後見と任意後見の使い分け
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの種類があります。これらを状況に応じて適切に使い分けることが重要です。法定後見は、すでに判断能力が低下している方のために家族などが申し立てるもので、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。一方、任意後見は、判断能力があるうちに本人自身が将来に備えて契約を結ぶものです。
本人に十分な判断能力がある早い段階で将来の認知症に備えたい場合は、任意後見契約がお勧めです。任意後見契約では、本人が信頼できる人を後見人に指定でき、後見人の権限範囲も本人の希望に合わせて設定できるというメリットがあります。

適切な後見人の選択と複数後見の活用
成年後見人には、親族後見人と専門職後見人があり、状況に応じて適切に選択することが重要です。親族後見人のメリットは、本人の意向や生活状況をよく理解していることや、報酬が不要または低額で済む場合が多いことです。一方、専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)は、法律や福祉の専門知識を活かした適切な財産管理や身上保護が期待できます。
成年後見制度において揉めないために
すでに判断能力が低下している場合や、任意後見契約を結ぶ機会を逃した場合は、法定後見制度を利用することになります。どちらの制度が適切かは、本人の判断能力の状態や家族状況、財産状況などを考慮して判断しましょう。専門家に相談することで、最適な選択ができます。
Victim
成年後見制度利用する人の心理

制度利用への
心理的ハードルを乗り越える
成年後見制度の利用を検討する際、「親が認知症と認定されることへの抵抗感」「家族の問題を外部に知られることへの抵抗」「親族間の意見の相違による緊張」などの心理的ハードルを感じる方は少なくありません。特に親の判断能力の低下を公的に認めることは、子としても心情的に受け入れがたい部分があるかもしれません。

制度を活用した
安心できる親の生活の実現
成年後見制度を適切に活用することで、認知症の親に安心できる生活環境を提供することができます。成年後見人が財産管理を担うことで、親の資産を守りながら必要な生活費や医療・介護サービスの費用を適切に支出することが可能になります。また、不要な契約の解除や新たな詐欺被害の防止など、様々なリスクから親を守ることができます。
Sample
Price
成年後見制度の利用費用の相場

成年後見制度の一般的な費用
成年後見制度を利用する際には、申立費用と後見人報酬の2種類の費用がかかります。申立て費用は、申立手数料(収入印紙800円)、登記手数料(2,600円)、郵便切手代(約3,000円)、戸籍謄本等の取得費用(1通450円程度)、診断書作成料(5,000〜20,000円程度)などがあり、全体で2〜5万円程度が目安です。手続きの中で鑑定費用がかかる可能性もあります。
後見人報酬は、本人の財産状況や後見事務の複雑さによって異なりますが、一般的な目安として月額2〜5万円程度です。親族が後見人になる場合は報酬を請求しないケースもあります。
また、申立てを弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用(15〜30万円程度)がかかります。複雑なケースや財産が多い場合はさらに高額になることもあります。ただし、本人の財産から支払うことが一般的です。


信頼できる専門家の選び方
成年後見制度のサポートを依頼する専門家選びでは、まず成年後見の実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
成年後見制度に関するよくあるご質問
Q
成年後見人はどのような人が選ばれますか?
成年後見人は、本人の状況や財産の内容、家族関係などを考慮して家庭裁判所が総合的に判断して選任します。
親族が選ばれるケースと、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるケースがあります。親族後見人のメリットは、本人の意向や生活状況を理解していること、報酬が少額または不要な場合が多いことです。一方、専門職後見人は、法律や福祉の専門知識を活かした適切な財産管理や身上保護が期待できます。
以下のような場合は、専門職後見人が選ばれることが多いです。
- 財産が高額または複雑な管理が必要な場合
- 親族間に対立や利益相反がある場合
- 相続や遺産分割の問題がある場合
- 親族の中に適任者がいない場合
最近では、親族と専門職の双方を後見人に選任する「複数後見」も増えています。例えば、親族が日常的な見守りを担当し、専門職が財産管理を担当するといった役割分担が可能です。
家庭裁判所は、本人の権利と財産を守るために最適な後見人を選任するという観点で判断しますので、個々のケースに応じた選任がなされます。
Q
成年後見制度を利用すると、親はどのような制限を受けますか?
成年後見制度を利用すると、本人(親)の行為能力に一定の制限が生じます。
特に「後見」類型では、日常生活に関する行為を除き、本人が単独で行った法律行為は取り消すことができるようになります。
具体的な制限は類型によって異なります:
後見の場合(判断能力が欠けている状態)
- 財産管理に関する契約行為が制限される(預貯金の引き出し、不動産の売買など)
- 日常生活に関する小さな買い物(食料品の購入など)は可能
- 選挙権は維持されるが、公務員になる資格や医師・弁護士などの資格が制限される場合がある
保佐の場合(判断能力が著しく不十分な状態)
- 民法で定められた重要な行為(借金、不動産売買など)に保佐人の同意が必要
- 日常的な金銭管理や契約は単独で可能
補助の場合(判断能力が不十分な状態)
- 家庭裁判所が定めた特定の法律行為のみ補助人の同意が必要
- それ以外の行為は制限されない
これらの制限は本人を守るためのものですが、本人の意思を尊重する運用も重視されています。成年後見制度を検討する際は、本人の自己決定権と保護のバランスを考慮することが大切です。
Q
成年後見制度は本人が亡くなったらどうなりますか?
成年後見制度は本人の死亡によって当然に終了します。
本人が亡くなると、成年後見人の権限も終了し、以下のような手続きが必要になります。
- 家庭裁判所への死亡報告: 成年後見人は本人の死亡を知った日から2週間以内に家庭裁判所に報告書を提出する必要があります。
- 最終報告書の提出: 後見事務の最終報告書を作成し、家庭裁判所に提出します。これには最後の財産状況や後見人報酬の報告が含まれます。
- 財産の引継ぎ: 本人の財産は相続人に引き継がれます。成年後見人は相続人が確定するまでの間、財産を保管する義務があります。
- 後見登記の閉鎖: 法務局で成年後見登記が閉鎖されます(特別な手続きは不要)。
成年後見人自身が相続人である場合でも、成年後見人としての立場と相続人としての立場は区別して対応する必要があります。また、成年後見人は相続人ではない限り、遺言執行者にならない限り、葬儀や相続手続きを行う権限はありません。