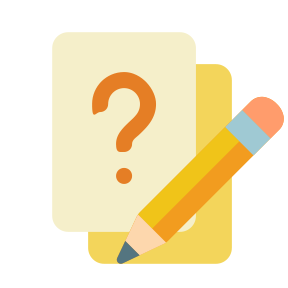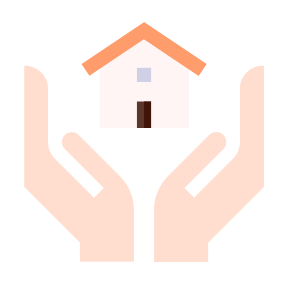遺言執行者になったらすべき7つの義務と手続き

突然遺言執行者に指名されて
戸惑っていませんか?
遺言執行者に指名されたものの、「何から始めればよいのか分からない」「法的な手続きが複雑で不安」といったお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。遺言執行者として適切に役割を果たし、被相続人(亡くなった方)の意思を実現したい方へ、弁護士法人エミリアが解決いたします!
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
遺言執行者になったらまず知るべきこと
遺言執行者に指定された場合、まず専門家に相談することをお勧めします。弁護士は遺言執行に必要な法的知識を持ち、適切な手続きについて的確なアドバイスができます。また、相続財産の調査方法や遺産目録の作成方法、相続人との適切なコミュニケーション方法についても助言可能です。専門家のサポートを受けることで、無駄な時間や労力を省き、トラブルを未然に防ぐことができます。弁護士との相談は、円滑な遺言執行の第一歩となります。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために被相続人から指定された人のことです。民法第1012条では「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています。遺言執行者は相続人の代理人ではなく、被相続人の意思を実現するための独立した立場にあり、遺言内容を優先して執行する義務があります。特別な資格は不要ですが、被相続人が信頼している人物が選ばれます。
遺言執行者の特徴

被相続人から信頼されている

法的手続きの知識がある

中立的な立場で職務を遂行できる

相続人との調整能力がある

責任感が強く誠実である
To Do
遺言執行者になったらすべき7つのこと

遺言書の確認と就任手続き
遺言執行者に指定されたら、まず遺言書の内容を確認し、就任の意思を決めましょう。承諾する場合は家庭裁判所に就任の申出をします。自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要ですが、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言では不要です。
Point
就任を決めたら、すぐに相続人全員に就任通知を送付することが重要です。通知には遺言執行者の氏名・住所、遺言の要旨、就任日などを記載し、内容証明郵便で送ることでトラブル防止になります。この初期段階での丁寧な対応が、後の円滑な執行につながります。

相続財産の調査
と目録作成
被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、動産などすべての財産を調査し、遺産目録を作成します。この調査は正確に行う必要があり、金融機関や法務局での手続きも含まれます。目録完成後は相続人に交付し、財産内容を共有します。

相続財産の
管理と保全
遺言が執行されるまでの間、相続財産を適切に管理・保全する義務があります。例えば、不動産の管理、貴重品の保管、債権の取り立てなどを行います。この管理義務は「善良な管理者の注意」をもって行うことが求められます。

遺言内容に従った
財産分配の準備
遺言の内容を確認し、特定遺贈や相続分の指定など、被相続人の意思を実現するための準備を行います。遺贈の履行や相続分の引渡しのために必要な書類を収集し、手続き方法を確認します。

預貯金・有価証券
の名義変更手続き
被相続人名義の預貯金や有価証券について、遺言の内容に従って名義変更の手続きを行います。金融機関ごとに必要書類や手続きが異なるため、事前に確認が必要です。一般的には遺言書の写し、被相続人と相続人の戸籍謄本、遺言執行者証明書などが必要です。

不動産の名義変更
登記手続き
不動産がある場合は、遺言の内容に従って名義変更登記を行います。必要書類を収集し、登記申請書を作成して法務局へ申請します。この手続きには専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することも検討すべきでしょう。

執行完了
の報告
すべての手続きが完了したら、相続人に対して執行の結果を報告します。この報告は書面で行うことが望ましく、執行した内容や使用した費用などを明確に示します。報告書はトラブル防止のためにも丁寧に作成し、保管しておきましょう。
Point
Point
遺言執行における2つのポイント

法的な権限と責任を理解する
遺言執行者は法的に「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を持ちます。この権限と責任の範囲を正確に理解することが重要です。相続人の意向よりも遺言内容を優先する義務があり、被相続人の意思を忠実に実現することが求められます。弁護士に相談することで、権限と責任の範囲をより明確に理解できます。

適切な進行管理と記録保持
遺言執行は複数の手続きを同時進行で行うこともあり、適切な進行管理が重要です。各手続きの進捗状況を記録し、必要書類を整理しておくことで、スムーズな執行が可能になります。また、相続人からの問い合わせにも適切に対応できるよう、執行内容の記録も丁寧に保管することが重要です。
遺言執行者の鍵とは?
遺言執行者は相続人の代理人ではなく、被相続人の意思を実現するための独立した立場です。この立場を理解し、中立性を保ちながら職務を遂行することが、円滑な遺言執行の鍵となります。
Victim
遺産分割で苦しむ相続人の心理

責任と不安に
向き合う方法
遺言執行者になると、重要な責任を担うことへの不安や、相続人との関係悪化への懸念など、様々な感情が生じることがあります。これらの感情は自然なものであり、専門家のサポートを受けながら冷静に対応することが大切です。相続人とのコミュニケーションを丁寧に行い、透明性を保つことで信頼関係を築けます。

円滑な
遺言執行のために
遺言執行は被相続人の最後の意思を実現する重要な役割です。この役割を通じて、亡くなった方の想いを形にする手助けをするという意義を見出すことができます。弁護士のサポートを受けながら、法的に適切な対応をとることで、遺言執行者としての役割を果たし、すべての関係者にとって納得のいく結果につなげることができます。
Sample
Price
遺言執行にかかる費用の相場

遺言執行にかかる一般的な費用
遺言執行における専門家への依頼費用は、財産の規模や複雑さによって大きく異なります。弁護士に依頼する場合、基本報酬として30〜50万円程度、財産額に応じた報酬として相続財産の1〜3%程度が一般的な相場です。司法書士や税理士への依頼費用も別途発生する場合があります。費用は必要な手続きや相続財産の規模によって増減するため、事前に見積もりを取ることが重要です。


信頼できる専門家の選び方
遺言執行のサポートを依頼する専門家選びでは、まず遺言執行の実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
遺言執行に関するよくあるご質問
Q
弁護士に依頼せず、自分だけで遺言執行はできますか?
弁護士に依頼せず、自分だけで遺言執行はできますか?
基本的な手続きは自分でも可能ですが、法律知識がない場合は複雑な手続きに困難を感じることが多いです。特に、不動産の名義変更や相続人との調整が必要な場合は専門家のサポートが役立ちます。まずは弁護士に相談し、自分でできる範囲とサポートが必要な部分を明確にすることをお勧めします。
Q
遺言執行にかかる費用は相続財産から支払えますか?
遺言執行に必要な費用は、原則として相続財産から支払うことができます。
これは「遺言執行費用」として民法上も認められています。ただし、費用の額が相当であることが前提であり、高額な費用については相続人から異議が出る可能性もあります。透明性を保つために、費用については事前に相続人に説明し、理解を得ることが重要です。
Q
なぜ弁護士に相談すべきでしょうか?
弁護士は遺言執行に必要な法的知識と経験を持っています。
相続手続きは複雑で、法律の専門知識がなければ適切に行うことが難しい場合が多いです。弁護士に相談することで、手続きのミスや無駄な労力を避け、スムーズな遺言執行が可能になります。また、相続人との間でトラブルが生じた場合の対応方法についてもアドバイスを受けられます。