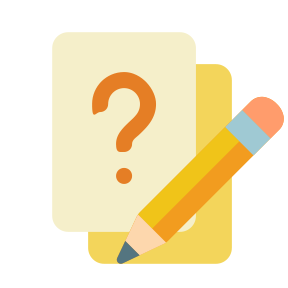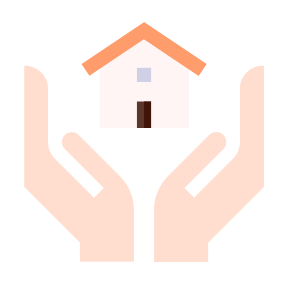相続人死亡で複雑化する遺産分割問題

数次相続の対処法
と解決策
相続は、遺産の引き継ぎを行う重要なプロセスですが、時には一筋縄ではいかないケースも発生します。その代表的な例が「数次相続」です。相続手続きが完了する前に相続人自身が亡くなるという事態は、特に高齢化が進む現代社会において珍しくありません。数次相続の基本から具体的な対応策、遺産分割の方法まで、専門的な視点から解説します。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
相続人死亡による
複雑な遺産分割を解決する
数次相続は、相続手続きが完了する前に相続人自身が亡くなり、複数の相続が連鎖する状況です。弁護士は数次相続に関する専門知識を持ち、複雑化した相続関係の整理から遺産分割協議の進め方まで適切にサポートできます。特に相続人が増加することで意見調整が難しくなるケースでは、第三者である専門家の客観的な立場が解決の糸口になります。専門家の力を借りることで、複雑な手続きの負担を軽減し、スムーズな遺産分割を実現することができます。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
数次相続とは
数次相続とは、ある人(被相続人A)の相続手続が完了する前に、その相続人(B)が死亡し、さらに次の相続が発生する状況を指します。この場合、Bの相続人(C)は、AとBの両方の遺産を相続することになります。例えば、父(A)が亡くなり、その子(B)が相続手続き中にBも亡くなった場合、Bの子(C)はAとB両方の遺産を相続することになります。数次相続では相続関係が複雑化し、相続人の増加による遺産分割協議の難航、相続登記手続きの複雑化、相続放棄の期限管理といった問題が生じます。なお、数次相続と混同されやすい「代襲相続」は、相続開始前に相続人が死亡している場合に適用される制度で、時系列が異なる点が大きな違いです。
数次相続の特徴

複数の相続が連鎖的に発生する
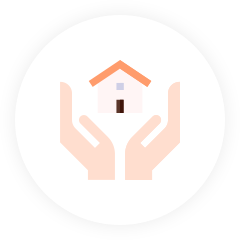
相続人の数が増加し、遺産分割協議が複雑化する

続登記手続きが複数段階になる

各相続について別々の相続放棄手続きが必要

相続関係の把握が難しくなる
To Do
数次相続に対応するための5つの方法

相続関係
を整理する
まずは複雑な相続関係を整理しましょう。被相続人と相続人の関係を時系列で示した相続関係図を作成し、全体像を把握します。合わせて、被相続人と全ての相続人の戸籍謄本を収集して、正確な相続関係を確認しましょう。
Point
相続関係の整理は、数次相続を解決するための第一歩です。特に複数の相続が重なると、誰が誰の相続人なのかが複雑になります。相続関係図を作成する際は、被相続人と相続人を時系列で図示し、各相続の開始日(死亡日)も明記しましょう。また、数次相続では多くの戸籍謄本が必要になるため、早めに収集を始めることが重要です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、各相続人の現在の戸籍謄本など、必要書類を漏れなく準備しましょう。この段階で正確な整理を行っておくことで、後の手続きがスムーズに進みます。

各相続の財産
を特定する
各被相続人がどのような財産を持っていたかを特定します。不動産、預貯金、有価証券などの財産や、借金などの債務も含めて正確に把握しましょう。特に、第一次相続の被相続人の財産が第二次相続でどのように引き継がれるかを整理することが重要です。

遺産分割協議
の進め方を決める
数次相続における遺産分割協議の進め方を決めます。原則として各相続ごとに協議を行いますが、状況によっては同時に進めることも可能です。相続人が複数いる場合は、全員の参加と合意が必要なため、早めに連絡を取り、協議の場を設けましょう。

相続登記の方法
を検討する
不動産の相続登記をどのように行うかを検討します。原則として各相続ごとに段階的に登記を行いますが、条件によっては中間省略登記も可能です。登記に必要な書類(遺産分割協議書、戸籍謄本、固定資産評価証明書など)を準備し、適切な方法で登記申請を行いましょう。

必要に応じて専門家
に相談する
数次相続は複雑な手続きが多いため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。特に相続人間で意見が対立している場合や、相続財産が複雑な場合は、専門家のサポートが問題解決の鍵となります。早めの相談が後々のトラブル防止につながります。
Point
Point
数字相続における2つのポイント

複数の遺産分割協議書の作成方法
数次相続では、原則として各相続ごとに遺産分割協議書を作成します。例えば、AさんとBさんの相続が発生している場合、「Aさんの遺産分割協議書」と「Bさんの遺産分割協議書」の2通を作成するのが基本です。ただし、状況によっては1通の協議書にまとめることも可能です。複数の協議書を作成する場合は、時系列順に作成し、各協議書に参加する相続人を明確にすることが重要です。また、各協議書で分割する財産を正確に特定し、特に第一次相続で取得した財産が第二次相続の対象になる場合は、その流れを明確に記載しましょう。

相続登記における中間省略登記の活用
数次相続での相続登記は、原則として各相続ごとに段階的に行いますが、一定条件下では「中間省略登記」という簡略化された方法が認められています。中間省略登記が認められやすい典型的なケースは、中間の相続人が1人だけで他に相続人がいない場合や、他の相続人全員が相続放棄している場合です。ただし、中間省略登記ができるかどうかは個別の状況によって異なりますので、不動産の所在地を管轄する法務局に事前に確認するか、専門家に相談することをお勧めします
数次相続の具体的な手続き
数次相続への対応プロセスは、相続関係の整理(1〜2週間)、財産調査(2〜4週間)、遺産分割協議の準備と実行(1〜3ヶ月)、相続登記などの手続き(1〜2ヶ月)という流れで進行します。シンプルなケースで3〜6ヶ月、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。
数次相続では多くの書類が必要となります。被相続人と相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを準備しましょう。特に戸籍謄本は複数世代分必要になるため、早めの収集が重要です。
Victim
数次相続に関する相続人の心理

複雑化する手続きへの
不安と負担
数次相続に直面すると、複雑な手続きへの不安や精神的・時間的負担を感じる方が多いです。「どの相続から手をつければよいのか分からない」「必要書類が多すぎて収集が大変」「複数の相続人との調整が難しい」といった悩みは自然なことです。特に、通常の相続でさえ負担が大きいのに、それが複数重なると圧倒されてしまう気持ちも理解できます。

適切な対応による
円満な解決
数次相続は複雑ですが、適切な対応を取ることで円満に解決することができます。専門家のサポートを受けながら相続関係を正確に整理し、法的に適切な手続きを進めることで、将来的なトラブルを防ぎ、相続人全員が納得できる形での解決が可能になります。
特に、早い段階で専門家に相談することで、手続きの負担が軽減されるだけでなく、相続人間の対立を未然に防ぐことができます。弁護士は中立的な立場から相続人間の調整を行い、公平な遺産分割を実現するサポートをします。また、専門家のアドバイスを受けることで、税金面でのメリットを得られる可能性もあります。
Sample
Price
数字相続にかかる費用の相場

数次相続の一般的な費用
数次相続にかかる費用は、自分で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。自分で行う場合の主な費用は、戸籍謄本等の取得費用(1通450円程度)、不動産登記の登録免許税(不動産評価額の0.4%)、その他郵送料や交通費などです。
弁護士に依頼する場合は、相続の複雑さや財産の額によって料金が変わりますが、一般的には着手金として30〜50万円程度、財産額に応じた報酬として相続財産の5~15%程度が一般的な相場です。数次相続は通常の相続よりも手間がかかるため、若干割増になることもあります。


信頼できる専門家の選び方
数次相続のサポートを依頼する専門家選びでは、まず相続、特に数次相続の実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
数次相続に関するよくあるご質問
Q
数次相続と代襲相続の違いは何ですか?
数次相続と代襲相続は、相続人が死亡するタイミングが大きく異なります。
相続人(A)の死亡後に相続人(B)が死亡した場合に発生します。つまり、Bは一度Aの相続人となり、その後Bも死亡して相続が発生するという時系列です。
一方、代襲相続は、被相続人(A)が死亡する前に法定相続人になるはずだった人(B)が既に死亡している場合に、その子(C)が代わりに相続人となる制度です。この場合、Bは相続開始前に既に亡くなっているため、Aの相続人となる機会自体がありません。
具体例で説明すると、父親Aが亡くなった後、その子Bが相続手続き中に死亡した場合は数次相続です。BはAの相続人となった後で死亡しているからです。しかし、Aが亡くなる前にBが既に死亡していた場合は代襲相続となり、Bの子Cが直接Aの相続人となります。
手続き上の違いとしては、数次相続では原則としてAからBへ、BからCへという2段階の相続手続きが必要になります。一方、代襲相続ではCが直接Aの相続人となるため、1段階の手続きで済みます。この違いを理解することで、適切な相続手続きを進めることができます。
Q
数次相続において相続放棄はどのように行うべきですか?
数次相続における相続放棄は、各相続ごとに別々の手続きが必要です。具体的には以下のようになります
まず、各相続は独立したものとして扱われるため、第一次相続(AからBへの相続)と第二次相続(BからCへの相続)は別々に考える必要があります。Cが両方の相続を放棄したい場合は、それぞれについて相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄の期限は、「自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内」と民法で定められています。数次相続の場合、第一次相続と第二次相続で知った時期が異なることもあるため、それぞれの期限管理が重要です。
手続きは以下の通りです。
- 被相続人ごとに別々の相続放棄申述書を作成します。
- それぞれの被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します(同じ家庭裁判所になることもあります)。
- 申述書には、どの被相続人の相続を放棄するのかを明確に記載します。
なお、第一次相続を放棄すると、その財産は他の相続人に移るため、第二次相続の対象からは外れます。しかし、第二次相続だけを放棄しても、第一次相続の権利や義務には影響しません。つまり、CがBの相続を放棄しても、BがAから相続した財産についてのCの権利は失われないというケースも考えられます。
相続放棄は一度行うと撤回できない重大な決断です。特に数次相続では影響関係が複雑になるため、専門家に相談した上で判断することをお勧めします。
Q
1通の遺産分割協議書で複数の相続をまとめることは可能ですか?
はい、1通の遺産分割協議書で複数の相続をまとめることは可能です。ただし、記載方法に注意が必要です。
1通にまとめる場合のポイントは以下の通りです。
- 被相続人の明確な区別: 協議書の冒頭で、各被相続人(例:AさんとBさん)の情報を明確に区別して記載します。例えば、最初にAさんの情報(氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所地・本籍地)を記載し、次にBさんの情報を「A相続人兼被相続人」として記載します。
- 財産の明確な区別: 各被相続人の財産を明確に区別して記載します。「Aさんの財産」と「Bさんの財産」という見出しをつけ、それぞれの財産と分割方法を明示します。
- 相続人の立場の明確化: 署名欄では、各相続人の立場を明確にします。例えば、CさんがBさんの相続人である場合、「B相続人 C」として署名・押印します。
- 相続関係の説明: 協議書の冒頭または別紙で、相続関係を説明する図や文章を添付すると、理解しやすくなります。
このように明確に区別して記載することで、1通の協議書でも複数の相続を適切に処理することができます。ただし、相続関係が非常に複雑な場合や多数の相続人が関わる場合は、誤解や混乱を避けるために、別々の協議書を作成する方が安全な場合もあります。
また、法務局での登記手続きの際に、1通にまとめた協議書が受け付けられるかどうかは、各法務局の判断によることもあります。不安がある場合は、事前に法務局に確認するか、専門家に相談することをお勧めします。