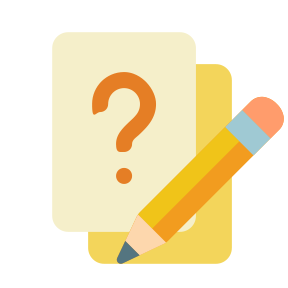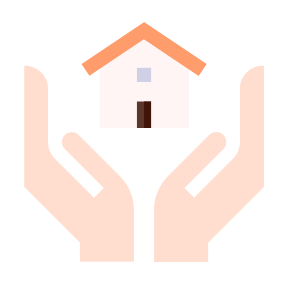遺留分侵害に気づいたらどうすればよいか

発見された不平等な遺言への対処法と解決策
遺言書を開いた瞬間、「えっ、これでは私の取り分がほとんどない…」と驚くことがあります。今すぐ大切な家族が残した遺言が、法律で保障されているはずの最低限の取り分「遺留分」を侵害している可能性に対応しましょう。遺留分侵害に直面した際の対処法から請求手続き、そして円満な解決策までを詳しく解説します。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
遺留分侵害問題
を解決する
遺留分とは、配偶者や子などの一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。弁護士は遺留分侵害に関する専門知識を持ち、適切な請求方法や解決策を提案できます。特に財産評価が複雑なケースや、相手方との交渉が難航している場合には、専門家のサポートが解決の糸口になります。専門家の力を借りることで、法的に適切な請求手続きを進め、あなたの権利を守りながら円満な解決を目指すことができます。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分のことです。民法で定められたこの制度は、被相続人(故人)の財産処分の自由と、相続人の生活保障のバランスをとるために設けられています。具体的に、遺留分は配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)に認められており、その割合は法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)となります。例えば、妻と子2人が相続人の場合、妻の法定相続分は1/2、子はそれぞれ1/4ですが、この場合の遺留分は、妻が1/4(法定相続分の1/2)、子がそれぞれ1/8(法定相続分の1/2)となります。遺留分は法律によって強行的に保障された権利であり、被相続人の意思によって排除することはできません。ただし、遺留分を侵害する遺言も基本的には有効であり、遺留分権利者が「遺留分侵害額請求」という手続きを取って初めて、侵害された分の回復が可能になります。
遺留分侵害の特徴

特定の相続人に財産が集中する遺言内容
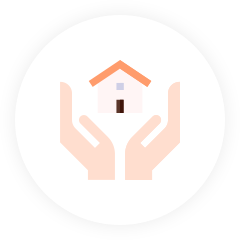
遺留分権利者(配偶者、子、親)の取り分が最低限より少ない

遺言書で「遺留分を認めない」と書かれていても無効

自動的に救済されず請求手続きが必要

気づいてから1年または相続開始から10年の時効がある
To Do
始める遺留分侵害への5つの方法

遺留分を正確
に計算しよう
まずは自分の遺留分を正確に計算しましょう。遺留分の計算は以下の手順で行います。遺産の総額を確定し、債務を差し引き、特別受益(生前贈与など)を加算し、寄与分を差し引いて基礎財産を算出します。その上で法定相続分を計算し、その法定相続分に遺留分率(配偶者・子は1/2、直系尊属のみの場合は1/3)をかけます。
Point
遺留分の計算は複雑ですが、自分の権利を守るために必須のステップです。特に「特別受益」と呼ばれる生前贈与や「寄与分」と呼ばれる被相続人の財産維持・増加への貢献は、遺留分計算に大きく影響します。特別受益については、相続開始前の10年間にされた贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)、それ以前でも遺留分侵害の意図がある場合は計算の基礎財産に含まれます。

速やかに財産目録
を作成しよう
遺留分侵害額を正確に計算するためには、遺産目録の作成と財産の適正な評価が不可欠です。遺産目録には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、貴金属など、被相続人が所有していたすべての財産を記載しましょう。財産の調査方法としては、預貯金は金融機関への照会、不動産は登記簿謄本の取得、有価証券は証券会社への照会などがあります。

遺留分侵害額を算出しよう
遺留分侵害額の計算は、「遺留分 – 相続によって実際に取得した財産額」という式で行います。例えば、あなたの遺留分が800万円であるのに、実際に相続できた財産が300万円の場合、遺留分侵害額は500万円となります。この算出には、特別受益(生前贈与など)や寄与分の評価も含まれるため、専門的な判断が必要なケースも多いです。なお、平成30年の民法改正により、遺留分侵害額請求は原則として金銭での支払いを求めるものとなりました。

速やかに相手方
へ請求しよう
遺留分侵害額が確定したら、受遺者や受贈者(遺言によって財産を取得した人)に対して請求書を送付しましょう。内容証明郵便を使用すると、後々のトラブル防止になります。請求書には、遺留分侵害額請求の意思表示、請求者の氏名・住所、被相続人の氏名・死亡日、遺留分侵害額の計算根拠、具体的な請求金額、支払期限などを記載します。請求後は相手方と協議を行いますが、合意に至らない場合は調停や訴訟などの法的手続きを検討することになります。なお、遺留分侵害額請求権には時効(相続開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年)があるため、早めの行動が重要です。

今すぐ専門家
に相談しよう
遺留分侵害は法律的に複雑な問題であり、専門家への相談が解決への近道です。弁護士に相談することで、正確な遺留分の計算、最適な請求戦略の立案、法的書類の適切な作成、時効管理などのサポートを受けられます。また、弁護士が介入することで、感情的になりがちな相続問題の交渉が円滑に進むことがあります。特に、財産評価が難しいケースや、相手方との関係が複雑な場合は、早めの専門家への相談が問題解決の鍵となります。初回相談で状況を整理し、今後の対応方針を決めることから始めましょう。
Point
Point
遺留分侵害における2つのポイント

冷静かつ戦略的な対応策を考えよう
遺留分侵害に気づいたときは、感情的にならず冷静かつ戦略的に対応することが重要です。まず、自分が置かれている状況を客観的に分析しましょう。本当に遺留分が侵害されているのか、その侵害額はどの程度か、請求相手は誰か、相手との関係性はどうか、などを整理します。
次に、どのような解決策が最適かを考えましょう。必ずしも法的手続きだけが解決策ではありません。家族関係を維持したい場合は、まずは話し合いの場を設け、遺言の意図や背景について理解を深めることも大切です。遺言を残した被相続人の意思を尊重しつつも、法的に保障された自分の権利も守るというバランスを考えましょう。
また、請求のタイミングも重要です。相続開始直後は感情が高ぶっている時期ですので、少し時間をおいて冷静になってから対応することも一つの選択肢です。ただし、時効の問題があるため、あまり長く放置するのは危険です。

円満解決のための代替案を用意しよう
遺留分侵害額請求は法的権利ですが、家族間の関係を悪化させるリスクもあります。そこで、法的手続きに頼るだけでなく、円満解決のための代替案を用意しておくことが重要です。
例えば、一括での金銭支払いが難しい場合は、分割払いの提案をしましょう。「3年間で毎月○○万円ずつ」といった具体的な提案は、相手方にとっても検討しやすいものです。また、金銭ではなく、相当する価値の不動産や有価証券などで代物弁済することも選択肢の一つです。
遺留分侵害請求の具体的な手続き
遺留分侵害への対応プロセスは、遺留分の計算と侵害額の確定(1〜2週間)、相手方への請求と協議(1〜3ヶ月)、法的手続き(調停・訴訟)の検討と実行(3ヶ月〜1年)という流れで進行します。シンプルなケースで3〜6ヶ月、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。
請求に必要な書類としては、内容証明郵便による請求書、遺産目録と財産評価資料、相続関係を証明する戸籍謄本、遺言書の写しなどがあります。調停を申し立てる場合は、調停申立書と必要な証拠書類を家庭裁判所に提出します。訴訟になった場合は、訴状と証拠書類を地方裁判所に提出することになります。
Victim
遺言書作成に関する不安

遺留分請求による
家族関係悪化への不安
遺留分侵害額請求を行うことで、家族関係が悪化するのではないかという不安は多くの方が抱えるものです。「お金のことで家族と争いたくない」「故人の意思を尊重すべきではないか」という迷いから、権利行使をためらうケースも少なくありません。
このような不安に対しては、まず遺留分が法律で保障された権利であることを認識することが大切です。遺留分を請求することは、不当に自分の権利を主張しているわけではなく、法的に保障された最低限の取り分を求めているに過ぎません。

遺留分制度による
公平な相続の実現
遺留分制度は、相続において最低限の公平性を確保するための重要な制度です。この制度があることで、被相続人の意思だけでなく、相続人の生活保障という側面も考慮された相続が実現します。
弁護士のサポートを受けながら法的に適切な請求手続きを進めることで、あなたの正当な権利を守りながらも、円満な解決を目指すことができます。例えば、分割払いや代物弁済など、相手方の事情も考慮した柔軟な解決策を提案することで、双方が納得できる形での解決が可能になります。
Sample
Price
遺留分侵害額請求にかかる費用の相場

遺留分侵害額請求の一般的な費用
遺留分侵害額請求にかかる費用は、自分で行う場合と弁護士に依頼する場合で大きく異なります。自分で請求手続きを行う場合、内容証明郵便の送付費用(1,000〜2,000円程度)や戸籍謄本等の取得費用(1通300〜500円程度)などが主な費用となります。調停申立てをする場合は収入印紙代(1,200円程度)、訴訟を提起する場合は訴額に応じた印紙代(例:100万円の請求で1万円程度)がかかります。
弁護士に依頼する場合は、着手金と報酬金が一般的です。着手金は事案の複雑さや請求額によって異なりますが、20〜50万円程度が相場です。報酬金は、解決した金額の10〜20%程度が一般的です。


信頼できる専門家の選び方
遺留分侵害額請求のサポートを依頼する専門家選びでは、まず相続・遺留分に関する実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
遺留分侵害に関するよくあるご質問
Q
遺言で「遺留分を認めない」と書かれていた場合、遺留分請求はできないのですか?
遺言書に「遺留分を認めない」などの記載があっても、その条項は無効です。
遺留分は法律によって強行的に保障された権利であり、被相続人の意思によって排除することはできません。したがって、そのような記載があっても、遺留分侵害額請求を行うことができます。
ただし、遺言書の内容全体が無効になるわけではなく、遺留分を侵害する部分についてのみ、遺留分権利者からの請求があれば調整が必要となります。遺留分侵害額請求権は形成権といわれるもので、請求があって初めて効力が生じるため、遺留分権利者自身が請求手続きを取る必要があります。
なお、遺留分は放棄することも可能ですが、その場合は相続開始前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。無効な「遺留分を認めない」条項と、有効な「遺留分放棄」は全く異なる法的効果を持ちますので、注意が必要です。
Q
兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分が認められているのは、配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)のみです。したがって、被相続人に子どもがなく、親も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、彼らには遺留分がないため、遺言で全財産を他人に遺贈されても、遺留分侵害を理由に異議を唱えることはできません。
Q
遺言書で財産をすべて一人に相続させることはできますか?
遺留分侵害額請求の時効はどうなっていますか?
遺留分侵害額請求権には時効があります。具体的には以下の二つのうち、いずれか早い方が時効となります:
- 相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
特に1年の期間制限は非常に短いため、遺留分侵害に気づいたら、速やかに行動することが重要です。「知った時」とは、相続開始の事実と遺留分侵害の事実の両方を知った時点を指します。例えば、遺言書の開封時や、隠れていた生前贈与が発覚した時などが該当します。
時効を過ぎてしまうと、正当な権利があっても請求できなくなるため、遺留分侵害の可能性に気づいたら、早めに専門家に相談することをお勧めします。また、時効の中断のためには、単なる交渉ではなく、内容証明郵便による請求や調停申立てなど、法的に有効な手段を取ることが必要です。