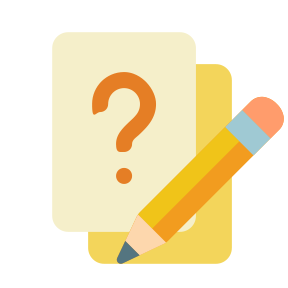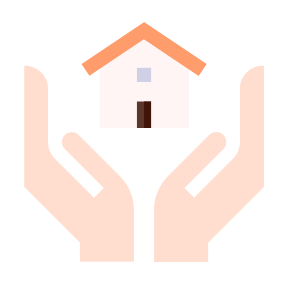家族信託で実現する障害のある子どもの将来

家族信託|親亡き後の資産管理と生活支援
障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、「自分が亡くなった後、子どもはどうやって生活していくのか」という不安は非常に大きなものです。特に財産管理や日常生活の支援について、誰がどのように担っていくのかという課題に直面します。今すぐ「親亡き後」の不安を解消する方法として注目されている「家族信託」について、活用方法を理解しましょう。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
家族信託で親亡き後の不安を解決する方法
家族信託は、財産の所有者(親)が信頼できる人(兄弟姉妹など)に財産を託し、障害のあるお子さんのために管理・処分してもらう仕組みです。弁護士は家族信託に関する専門知識を持ち、お子さんの状況に合わせた最適な信託スキームを提案できます。特に成年後見制度では対応が難しい柔軟な財産活用や、長期的な生活支援を実現したい場合に、専門家のサポートが解決の糸口になります。弁護士法人エミリアが解決いたします!

Case
What’s
家族信託とは
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を託し、その財産を特定の人(受益者)のために管理・処分してもらう仕組みです。障害のあるお子さんの場合、親が委託者となり、信頼できる家族や親族を受託者として、障害のあるお子さん(受益者)のために財産を管理する形が一般的です。家族信託の大きな特徴は、委託者が信託契約で財産の管理・処分方法について細かく指示できる点です。従来の成年後見制度では、財産の使い道が本人の生活に直接必要なものに限られ、不動産売却や高額支出には家庭裁判所の許可が必要でした。一方、家族信託では委託者の意思に基づいて柔軟な財産管理が可能であり、家庭裁判所の許可なく信託契約で定めた範囲内での資産運用や不動産売却もできます。
相続税の節税対策の特徴

親の意思を反映した柔軟な財産管理が可能
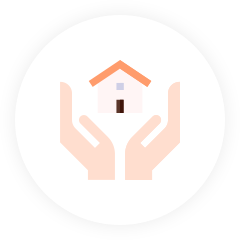
家庭裁判所の許可が不要で、迅速な判断可能

不動産など様々な財産を信託できる

次の受託者をあらかじめ指定できる

障害のあるお子さんの意思を尊重した支援可能
To Do
今すぐ始める家族信託の活用5つの方法

将来の課題
を明確にしよう
まずは障害のあるお子さんの将来の課題を明確にしましょう。「誰が財産管理をするのか」「日常生活の支援は誰が行うのか」「どのような生活を送って欲しいか」など、具体的な課題を洗い出します。特に障害の特性や程度、現在利用している支援サービスなどを考慮して、将来必要となるサポートを検討しましょう。将来の課題が明確になれば、家族信託の目的や方向性も決まってきます。
Point
親御さんが高齢になった時、そして親亡き後も含めた継続的な支援体制を構想する必要があります。障害のあるお子さんの年齢や障害の状況、成長の可能性、きょうだいの有無とその状況、親族との関係性など、多角的な要素を考慮しましょう。また、現在利用している障害福祉サービスの継続性や、将来的に必要となる可能性のある医療・介護サービスについても検討が必要です。

信託に適した
財産を選定しよう
家族信託に組み入れる財産を選定しましょう。自宅などの不動産、預貯金、有価証券、保険金など、様々な財産を信託することができます。特に障害のあるお子さんが住み続けたい自宅は、信託財産として組み入れることで居住権を確保しながら適切な管理が可能になります。

受託者を
選定しよう
信頼できる受託者を選定しましょう。兄弟姉妹やその配偶者、親族など、障害のあるお子さんのことをよく理解し、長期的に支援できる人を選ぶことが重要です。また、万が一の場合に備えて、次の受託者(第二受託者)も指定しておくと安心です。

信託契約の内容
を検討しよう
信託契約の具体的な内容を検討しましょう。財産の管理方法や使途、受益者であるお子さんへの給付条件(毎月の生活費の金額、医療費や特別な支出の取り扱いなど)、信託の期間、受託者の報酬、信託終了時の残余財産の帰属先などを具体的に決めていきます。特に障害のあるお子さんの特性や希望を考慮した内容にすることが重要です。

専門家に相談し
定期的に計画を見直す
家族信託は法的な専門知識が必要な制度です。弁護士や司法書士などの専門家に相談して、最適な信託スキームを設計してもらいましょう。特に障害者福祉制度との連携や税金面での影響など、専門的な観点からのアドバイスが必要です。また、信託契約書の作成や信託財産の名義変更などの手続きも専門家のサポートを受けると安心です。早めの相談が後々のトラブル防止につながります。
Point
Point
家族信託活用の2つのポイント

総合的な支援計画を立てよう
家族信託は財産管理の仕組みですが、障害のあるお子さんの生活支援全体の中に位置づけて考えることが大切です。障害年金などの公的支援、障害福祉サービス、医療サービスなどと家族信託を組み合わせた総合的な支援計画を立てましょう。
例えば、日常的な生活費は障害年金で賄い、医療費や特別な支出には信託財産からの収益を充てるなど、各制度の特徴を活かした計画が効果的です。また、特定贈与信託(障害者贈与信託)という税制優遇制度も活用できる場合があります。この制度では、障害のあるお子さんのために金銭を信託した場合、一定額(6,000万円)まで贈与税が非課税になります。
さらに、成年後見制度と家族信託を併用することで、より手厚い支援体制を構築することも可能です。例えば、財産管理は家族信託で行い、医療同意や福祉サービスの契約など、財産管理以外の法律行為については成年後見人がサポートするという形が考えられます。

早期からの計画的な取り組みの重要性
家族信託を長期間にわたって安定的に運用するためには、将来のリスクに備えた設計が重要です。特に考慮すべきポイントとして、受託者の高齢化や病気、家族関係の変化などがあります。
まず、受託者が高齢化した場合や病気になった場合の対応として、次の受託者(第二受託者)をあらかじめ指定しておくことが大切です。第二受託者は、現在の受託者が務められなくなった場合に、スムーズに引き継ぐことができる人を選びましょう。場合によっては、専門家(弁護士や司法書士)や信託銀行を指定することも検討の余地があります。
また、家族関係の変化(受託者の離婚や再婚など)によるリスクも考慮する必要があります。信託財産と受託者の個人財産は明確に区別され、受託者の債権者から信託財産が差し押さえられることはありませんが、受託者自身の状況変化によって適切な管理が難しくなる可能性もあります。そのため、信託契約に受託者の交代条件を明記しておくことも重要です。
相続税の節税対策で困らないために
家族信託の設定プロセスは、課題の整理と計画立案(1〜2ヶ月)、信託契約の設計(1〜2ヶ月)、信託契約の締結と財産移転(1〜2ヶ月)という流れで進行します。
具体的な手続きとしては、まず信託契約書を作成します。委託者・受託者・受益者の指定、信託財産の範囲と管理方法、財産の使途や条件、信託の期間などを詳細に記載します。次に、信託財産の名義変更手続きを行います。不動産の場合は法務局での登記変更、預貯金の場合は金融機関での名義変更が必要です。これらの手続きは専門家のサポートを受けながら進めるとスムーズです。
Victim
家族信託に関する不安

家族信託の
運用・管理の負担
家族信託を設定すると、受託者には信託財産の管理責任が生じます。「受託者の負担が大きくなりすぎないか」「長期間にわたって適切に管理できるか」という不安は自然なことです。特に障害のあるお子さんのための家族信託は、場合によっては数十年という長期間の運用が必要になります。

家族信託による
安心感の獲得
家族信託を適切に設計することで、「親亡き後」の不安を大きく軽減することができます。親の思いを反映した財産管理が可能になり、障害のあるお子さんの将来の生活基盤を確保することができます。弁護士のサポートを受けながら法的に有効な信託契約を作成することで、お子さんの特性や状況に合わせたオーダーメイドの支援体制を構築できます。
Sample
Price
家族信託にかかる費用の相場

家族信託設定の一般的な費用
家族信託の設定にかかる費用は、信託の内容や財産の種類によって異なります。一般的な費用の目安は以下の通りです。
相談・設計費用として、弁護士や司法書士に依頼する場合、30〜100万円程度が相場です。これには信託契約の設計、契約書の作成、アドバイスなどが含まれます。特に障害のあるお子さんのための家族信託は、公的支援との兼ね合いなども考慮する必要があり、専門的な知識が要求されます。
信託財産の名義変更に関する費用も必要です。不動産を信託する場合、登記費用として登録免許税(不動産評価額の0.4%)や司法書士報酬(5〜10万円程度)がかかります。預貯金や有価証券の場合は、金融機関によって手数料が異なりますが、一般的に数千円〜数万円程度です。


信頼できる専門家の選び方
家族信託のサポートを依頼する専門家選びでは、まず家族信託と障害者支援に関する実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。追加料金の発生条件や最終的な総額が明確に提示されるべきです。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
家族信託に関するよくあるご質問
Q
家族信託と成年後見制度はどちらが良いですか?
家族信託と成年後見制度には、それぞれ特徴とメリット・デメリットがあります。
どちらが良いかは、障害のあるお子さんの状況や家族の事情によって異なります。
家族信託のメリットは、親の意思を反映した柔軟な財産管理が可能な点です。例えば、「毎月いくらを生活費として使う」「住み慣れた自宅に住み続ける」など、具体的な指示ができます。また、家庭裁判所の許可なく不動産売却や資産運用ができるため、迅速な対応が可能です。
一方、成年後見制度は公的な制度で、家庭裁判所の監督があるため安全性が高いという特徴があります。しかし、財産の使い道が本人の生活に直接必要なものに限られ、高額な支出には裁判所の許可が必要など、制約も多くあります。
両制度を併用することも可能です。例えば、財産管理は家族信託で行い、医療同意や福祉サービスの契約など身上監護面は成年後見人がサポートするという形が考えられます。お子さんの状況や将来の見通しに合わせて、最適な選択または併用を検討しましょう。
Q
信頼できる受託者がいない場合はどうすればよいですか?
信頼できる家族や親族がいない場合でも、家族信託を活用する方法はあります。以下のような選択肢が考えられます。
専門家を受託者にする: 弁護士や司法書士などの専門家を受託者に指定することができます。専門的な知識や経験があり、中立的な立場で信託事務を遂行してくれるメリットがあります。ただし、報酬が必要になるため、信託財産からの支払いを計画的に設定する必要があります。
信託銀行を利用する: 一定規模以上の財産がある場合は、信託銀行による「民事信託サポート」などのサービスを利用する方法もあります。信託銀行が直接受託者になるわけではありませんが、受託者をサポートする形で専門的なアドバイスや事務支援を提供してくれます。
障害福祉サービス事業者との連携: 日常的な支援をしている障害福祉サービス事業者の関係者に相談し、連携する方法も検討できます。例えば、グループホームの運営法人や相談支援事業所などと協力関係を築き、見守りや助言をお願いすることが考えられます。
複数人による受託: 単独では受託者になることが難しい場合でも、複数人で役割分担して共同受託者となる方法があります。例えば、親族と専門家が共同で受託者となり、それぞれの強みを活かした運用が可能です。