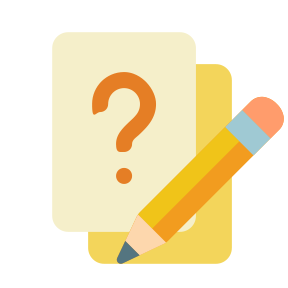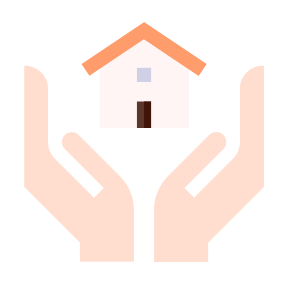不公平な遺産分割から相続権を守る方法

適正な相続分を確保するための実践ガイド
相続で最も揉めるのが、遺言が遺されていない場合に行われる遺産分割です。特に不公平な分割案を提示された場合、どう対応すべきか悩まれる方は少なくありません。あなたの相続権を守り、適正な相続分を確保するための行動を起こしましょう。
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破
ご相談件数
1000件
突破

こんなお悩み抱えていませんか?
Resolve
弁護士法人エミリアに
お任せください
お任せください
不公平な遺産分割
から相続権を守る方法
不公平な遺産分割案に直面した場合、まず知っておくべきことは、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないという原則です。弁護士は相続法に関する専門知識を持ち、あなたの権利を守るための適切な対応策を提案できます。特に感情的になりがちな親族間の交渉では、第三者である専門家の客観的な意見が解決の糸口になることが多いです。

Case
Case
不公平な遺産分割とは
不公平な遺産分割とは、法定相続分や被相続人の意思に反して、特定の相続人が不当に有利または不利になるような遺産の分け方のことです。民法では相続人の法定相続分が明確に定められており、配偶者と子がいる場合は配偶者が1/2、子が1/2という割合になります。もちろん相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる分割も可能ですが、その同意が強制や誤解に基づくものであってはなりません。
不公平な遺産分割の特徴

法定相続分と大きく異なる分割案が提示される
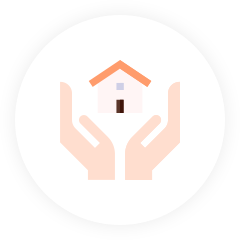
特定の相続人のみが優遇される

相続財産の一部が隠されている可能性がある

感情的な圧力や家族の事情が持ち出される

十分な協議の機会が与えられない
To Do
不公平な遺産分割から身を守るための5つの方法

相続財産
の全体像を把握する
まずは相続財産の全体像を正確に把握しましょう。預貯金、不動産、有価証券、貴金属、美術品、負債など、すべての財産と債務を調査します。財産の隠匿を防ぐためにも、預金通帳や登記簿謄本などの証拠資料を収集しておくことが重要です。
Point
相続財産の調査は、公平な分割の土台となる重要なステップです。特に相続人同士の信頼関係に不安がある場合は、金融機関への照会や法務局での不動産調査などを積極的に行いましょう。財産調査は弁護士に依頼することも可能です。また、調査結果は文書にまとめ、写真や資料などの証拠と共に保管しておくことが大切です。これらの情報は後の交渉や調停の際に重要な資料となります。

法定相続分
を確認する
民法で定められた法定相続分を確認しましょう。相続人の構成によって法定相続分は異なりますが、これが分割協議がまとまらない場合に裁判所が決めるときの基準になるため、公平な分割の指標となります。また、遺言書がある場合はその内容を確認し、必要に応じて遺留分を主張する準備をしましょう。

寄与分と特別受益
を考慮する
相続分を調整する要素として、寄与分と特別受益があります。寄与分は被相続人の財産維持・増加に貢献した場合に認められる追加分で、特別受益は生前贈与などで既に受け取った利益のことです。これらを正確に把握し、公平な分割案の作成に活用しましょう。

具体的な代替案
を作成する
不公平な案に対しては、具体的な代替案を提示することが効果的です。法定相続分を基準に、寄与分や特別受益を考慮した公平な分割案を作成しましょう。感情的な主張ではなく、数字や法的根拠に基づいた客観的な提案が説得力を持ちます。

専門家に相談し
法的手続きを検討する
話し合いでの解決が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。弁護士は法的知識に基づいた交渉を代行してくれるだけでなく、必要に応じて家庭裁判所への調停申立てなどの法的手続きをサポートしてくれます。早い段階での専門家への相談が問題解決の鍵です。
Point
Point
相続分を守るための2つのポイント

全員一致の原則を理解して毅然とした態度を取る
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。これは民法で定められた大原則です。「多数決で決まった」「親族会議で決定した」といった圧力があっても、法的には無効ですので、毅然とした態度で対応しましょう。感情的にならず、「法律に基づいた公平な分割を希望している」という原則的な立場を維持することが重要です。

証拠の収集と記録を徹底する
相続争いでは、証拠が決め手となります。相続財産に関する資料はもちろん、話し合いの内容や相手の言動についても記録を残しておきましょう。具体的には、話し合いの日時・場所・参加者・内容をメモに残す、重要な会話は録音する(事前に相手に伝えることが望ましい)、メールやLINEでのやり取りを保存する、などの方法があります。
相続分を守るために
感情的にならず、「法律に基づいた公平な分割を希望している」という原則的な立場を維持することが重要です。無理な妥協や感情的な対立は避け、必要なら一時的に話し合いを中断して冷静さを取り戻すことも大切です。相続人としての権利は法律で保障されていることを忘れないでください。
Anxiety
相続権を守れない相続人の心理

不公平な分割案に
直面したときの感情的苦痛
不公平な遺産分割案に直面すると、怒り、悲しみ、裏切られた感覚、家族関係への不信感など、様々な感情が生じるものです。「家族なのに金銭的なことで争うべきではない」「親族関係が壊れるのではないか」といった葛藤も生まれます。こうした感情は自然なものですが、冷静な判断を妨げることもあります。感情に任せた言動は問題解決を難しくするため、一呼吸置いて冷静に考えることが大切です。必要なら信頼できる第三者に気持ちを打ち明け、客観的な視点を得ることも有効です。

法的な解決による
公平な相続の実現
不公平な遺産分割に対して法的手段を取ることは、決して家族を裏切る行為ではありません。むしろ、被相続人の財産を公平に分配するという相続法の本来の目的に沿った行動です。弁護士のサポートを受けながら法的に適切な対応をとることで、感情的な対立を最小限に抑えつつ、あなたの正当な権利を守ることができます。法的解決は時に時間がかかりますが、最終的には法律に基づいた公平な分割が実現します。この経験を通じて、将来の自分自身の相続対策について考えるきっかけにもなるでしょう。
Sample
Price
遺産分割にかかる費用の相場

遺産分割交渉・調停の一般的な費用
遺産分割問題に弁護士を依頼する場合の費用は、案件の複雑さや相続財産の額によって大きく異なります。一般的には、着手金として20〜50万円程度、報酬金として解決した相続財産の5〜10%程度が相場です。調停申立てには収入印紙代(1,200円程度)や郵便切手代なども必要です。
訴訟になると、着手金や報酬金が高額になり、裁判所への印紙代も相続財産の価額に応じて増加します。例えば5,000万円の遺産分割訴訟では、印紙代だけで15万円程度になることもあります。


信頼できる専門家の選び方
相続問題のサポートを依頼する専門家選びでは、まず相続に関する実績と経験を確認しましょう。料金体系の透明性も重要な判断材料です。無料相談を活用して、担当者の対応や専門知識を直接評価することで、信頼性の高い専門家を見極められます。複数の専門家に相談して比較検討することをお勧めします。
FAQ
FAQ
不公平な遺産分割に関するよくあるご質問
Q
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割はどうなりますか?
相続人の中に行方不明者がいる場合、通常の遺産分割協議を進めることができません。
この場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立て」を行い、行方不明者の権利を代理する管理人を選任してもらう必要があります。選任された管理人は、行方不明者の利益を考慮しながら遺産分割協議に参加します。
この手続きには、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、行方不明の事実や相続財産の存在を証明する資料を提出します。手続きには数ヶ月かかることが一般的で、管理人への報酬も必要です。行方不明者が長期間現れない場合は、「失踪宣告」という手続きを経て、法的に死亡したとみなすことも可能です。これらの複雑な手続きは専門家のサポートを受けることをお勧めします。
Q
兄弟の一人が遺産分割に全く協力してくれません。どうすればよいですか?
相続人の一人が遺産分割に非協力的な場合、以下のステップで対応することをお勧めします。
まず、書面やメールで遺産分割協議への参加を正式に要請します。日時・場所を具体的に提案し、返答期限を設けることで、誠意ある対応を促します。それでも応じない場合は、内容証明郵便で正式に協議参加を求めることで、法的手続きの前段階であることを認識させることが効果的です。
それでも協力が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停は強制力があり、呼出状が裁判所から送付されるため、無視することは難しくなります。調停でも解決しない場合は審判に移行し、裁判官の判断で遺産分割が決定されます。
非協力的な相続人への対応は、感情的にならず、法的手続きに沿って粛々と進めることが重要です。弁護士に相談することで、適切な対応方法のアドバイスや具体的な手続きのサポートを受けられます。
Q
親が他の兄弟に生前贈与をしていました。これは相続時に考慮されますか?
限定承認と相続放棄のどちらを選ぶべきかは、財産と借金の状況や相続人の意向によって異なります。
親から特定の兄弟に対して行われた生前贈与は、「特別受益」として相続時に考慮されます。特別受益は、遺産分割の際に一度相続財産に持ち戻して計算し、その後で各相続人の取り分を決定する仕組みになっています。これにより、生前贈与があった兄弟の相続分が調整され、公平な分割が実現します。
特別受益として考慮される主な生前贈与には、不動産や高額な金銭、事業資金、留学費用などがあります。ただし、通常の生活費や教育費、結婚祝い金(社会通念上相当な範囲)などは特別受益には含まれないのが一般的です。
特別受益を主張する場合は、贈与の事実と金額を証明する必要があります。贈与契約書、振込記録、不動産登記簿、当時の関係者の証言などが重要な証拠となります。証拠集めが難しい場合は、弁護士に相談することで適切な調査方法や主張の仕方についてアドバイスを受けられます。生前贈与が相続に与える影響を正確に把握し、公平な遺産分割を実現しましょう。